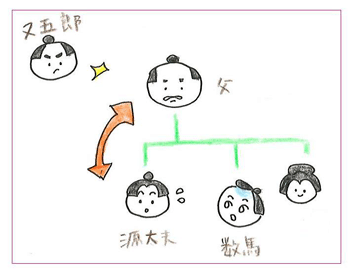嘆揋摙偪偺敪抂
偲偙傠偱丄偙偺乽埳夑墇偺揋摙偪乿丄尨場偼側傫偩偭偨偺偱偟傚偆丅
偦傕偦傕丄壨崌枖屲榊偲搉曈悢攏偼丄摨偠壀嶳斔庡丒抮揷拤梇偵巇偊傞丄偄傢偽巇帠拠娫丅偲偙傠偑枖屲榊偑悢攏偺掜丒尮懢晇傪撍擛嶦奞偟傑偟偨丅姲塱7擭乮1630擭乯7寧21擔栭偺弌棃帠偱偡丅
摉帪枖屲榊偼20嵨丄悢攏偼23嵨丅壧晳婈傗暥妝偱偼丄悢攏偵奩摉偡傞榓揷巙捗攏偼偝傢傗偐側晽杄丄枖屲榊偵奩摉偡傞戲堜屢屲榊偼憺憺偟偄晽杄偱墘偠傜傟傞偺偱側偐側偐婥偯偒傑偣傫偑丄幚偼枖屲榊偺傎偆偑庒偄偺偱偡丅嶦偝傟偨尮懢晇偼傑偩17嵨偱偟偨丅壗傪偒偭偐偗偵偙偺帠審偑婲偙偭偨偺偐偼傛偔傢偐偭偰偄傑偣傫丅
尮懢晇偼抮揷拤梇偺偍婥偵擖傝偺偍彫惄偝傫偱偟偨丅偦偺偙偲偐傜丄枖屲榊傕尮懢晇偺偙偲偑婥偵側偭偰偄偨偺偵尮懢晇偵偡偘側偔偝傟偰丄暊偑棫偭偰嶦奞偵媦傫偩丄偲偄偆愢傕偁傞傛偆偱偡丅
偲偙傠偑丄亀埳夑墇摴拞憃榋亁側偳偺偍幣嫃傗島庍側偳偺嶌傝暔偵側傞偲丄揋摙偪偺敪抂偑偐側傝嶌傝懼偊傜傟偰偟傑偆偺偱偡丅
偲偄偆偺偼丄亀埳夑墇亁偱偼丄嶦偝傟偨偺偼榓揷巙捗攏乮巎幚偺搉曈悢攏乯偺掜偱偼側偔丄晝偺峴壠丅戲堜屢屲榊乮巎幚偺壨崌枖屲榊乯偼榓揷壠偐傜壠曮偺搧傪扗偄庢傞偨傔偵峴壠傪朘偹傑偡偑幐攕偟丄偲偆偲偆嶦奞偵 |