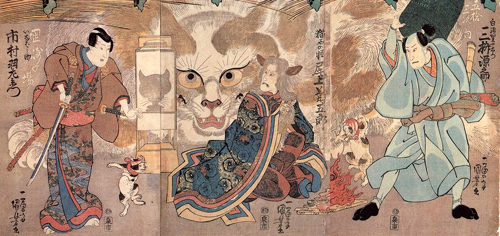岩にネコの爪跡
その「岡崎の猫」のくだりは愛知県豊田市の山間に建つ大鷲院(だいしゅういん)に伝わるお話がベースだろうといわれます。それは「同寺の住職がお葬式でお経をあげていると、真っ赤な口を耳まで開けた猫が棺の中に飛び込もうとした。住職は払子(ほっす、柄のついた仏具)で殴り、退散させたが、式を済ませて寺に帰ると飼い猫が顔を腫らし片目を潰していた。住職はさっそく猫を教え諭し、八丈岩に封じ込めた」というお話。お寺の裏山にはその八丈岩が今もあり、猫の爪跡というのが見られるそうです。
30年生きると・・・
こうした化け猫伝説と共に、いくつかの地方では「猫又(ねこまた)」という妖怪がいるとも信じられていました。猫は30年生きると尻尾の先が二股に割れ、猫又になるというのです。そのため、子猫のうちに尻尾を切ってしまう風習もあったようです。
「化け猫」も「猫又」も愛猫家にはなんとも不愉快なお話でしょうが、では猫はなぜそんなに恐れられたのでしょうか。
闇で光る瞳
まず猫の瞳は暗闇で光ります。夜中に境内などで催される「猫の集会」は灯りのない時代には相当不気味だったでしょう。それに目だけでなく、静電気で体まで光ることがあり、また目が針のように細くなるのも気味が悪かったかもしれません。
習性も仇に
高いところから平気で飛び降りたり、聞き耳を立てるような姿=猫は、顔を向こうに向け、耳だけこちらへ動かすことができますね。これらも魔性を感じさせます。さらにクールな性格や獲物を待ち伏せする狩りのパターンなど、猫にとっては当たり前の習性も仇になったようです。中世ヨーロッパでは、いわゆる「魔女狩」の時に、猫も悪魔の使いとされ、「歯に毒がある」とか「毛を吸い込んだら死ぬ」などと言われ、多くが犠牲になりました。
不道徳な生き物?
日本では「戸を開け始めたら化け猫」とも言われたようです。引き戸が多かった日本家屋では、いつの間にか戸を開けられるようになる猫もいたのでしょう。
また封建制に縛られていた昔の人々には、気ままで身勝手に見える猫は、忠実な犬などと違って、不道徳な生き物に思われ、それも猫の化け物化に拍車(はくしゃ)をかけたという見方もあるようです。 |